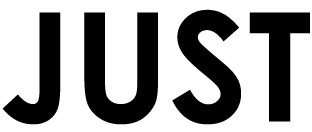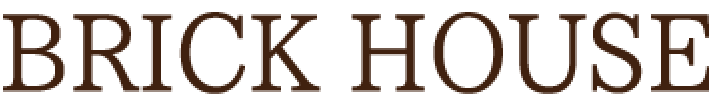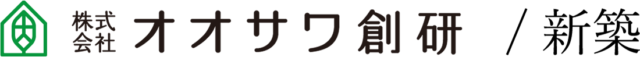マンション修繕積立金不足問題 - 知っておくべき現実と対策
投稿日:2025.10.12
こんにちは。不動産事業部の松島 豊です。
今回は、マンション修繕積立金不足問題 - 知っておくべき現実と対策について、わかりやすくご紹介いたします。
前回のブログはこちらから
■ 深刻化する修繕積立金不足の実態
驚くべき実態が明らかに!
国土交通省の調査(2024年6月発表)によると、必要な積立額に対して「不足している」と答えた管理組合が36.6%にも達しています。これは3年前の調査から増加傾向にあり、多くのマンションが構造的な資金不足に陥っている現実を浮き彫りにしています。
修繕積立金とは?
- 屋上の防水工事
- 外壁タイルの貼り替え
- エレベーター設備の交換
- 大掛かりな修繕工事に充てる重要な資金
積立金が不足すると、各戸の所有者が一時金として新たに負担しなければならず、数十万円~数百万円もの負担が発生する可能性があります。
■ 国の新たな対策と基準設定

2024年2月、国土交通省が重要な方針を発表!
- 修繕積立金の徴収額を段階的に引き上げる場合の増額幅を最大約1.8倍とする新基準を設定
- 「長期修繕計画作成ガイドライン」および「マンションの修繕積立金に関するガイドライン」を改訂
- 過去25年間で修繕積立金の平均額は約1.8倍の13,054円(月額) まで増加
この新基準は、地方公共団体が実施する管理計画認定制度にも盛り込まれる予定で、マンション管理の質的向上を目指した制度的な後押しが期待されています。
■ 管理委託費見直しの効果と必要性

支出の最適化が根本的な解決策!
管理組合の会計では、一戸当たりの収入は月1~2万円程度というマンションが多いのが実情です。しかし、その業務の多くを専門の管理会社に委託しているため、支出の大部分は管理委託費として計上されています。
驚きのデータ
- 複数の管理会社のサービスと費用を比較検討しているマンション:わずか24%
- 実際に切り替えを実施したマンション:18%
- 検討すらしていないマンション:76%
管理会社切り替えの効果
管理会社の切り替えに踏み切った管理組合では、平均3割の管理委託費削減を実現!これは年間数十万円から数百万円の支出削減につながり、修繕積立金不足の改善に直接的な効果をもたらします。
■ 大手系列管理会社からの脱却!

固定概念を見直そう!
ブランド力のある大手ディベロッパーが分譲したマンションでは、「系列の管理会社に管理を任せなければ資産価値が下がる」と懸念する住民も多くみられます。
しかし、この固定概念を見直し、競争原理を働かせることで、サービス品質の向上とコスト削減の両方を実現できる可能性があります。
管理組合の意識改革が必要
- 従来の「お任せ」体制からの脱却
- 積極的な経営判断の実施
特に小規模マンションでは管理委託費の影響が深刻
■ 大規模修繕の周期見直しという新たなアプローチ!
12年周期から15~18年周期へ
従来、大規模修繕は12年ごとに実施するのが一般的でしたが、建築技術の進歩と材料の長寿命化により、専門家の診断に基づいて15~18年周期に延長することも有効な対策として注目されています。
周期延長のメリット
- 修繕積立金の負担を分散
- より計画的な資金運用が可能
- 住民の経済的負担軽減
重要な注意点
この判断には専門的な知識が必要であり、定期的な建物診断と適切な維持管理が前提となります。単純に修繕を先延ばしにするのではなく、科学的根拠に基づいた計画的な判断が重要です。
■ マンション購入者への提言
購入前に必ず確認すべきポイント
- 修繕積立金の状況
- 現在の修繕積立金残高
- 長期修繕計画との整合性
- 管理組合の運営体制
- 意思決定プロセス
- 住民の参画度
- 管理会社の状況
- 選定プロセス
- 委託費の妥当性
- 過去の実績と今後の計画
- 大規模修繕の実施状況
- 今後の修繕計画
住民の積極的な参画が重要
場合によっては、入居後に管理組合の改革に積極的に参画する「覚悟」も必要かもしれません。住民の関心と参画が、マンションの資産価値維持と持続可能な管理運営の基盤となります。
■ 今後の展望と課題
単なる資金調達の課題を超えて
マンションの修繕積立金不足問題は、住民コミュニティの維持可能性に関わる本質的な問題です。
変革期を迎えるマンション管理
高齢化と人口減少が進む中で、マンション管理組合の運営体制自体も変革期を迎えています。
解決への道筋
- 制度的な後押し
- 住民意識の向上
- 専門家による適切なサポート
最も重要なこと
問題を先送りせず、その認識のもと全ての関係者が協力して持続可能な管理体制を構築していくことが求められています。
【まとめ】
修繕積立金不足問題は、単なる資金不足ではなく、マンションという資産を将来にわたって維持していくための本質的な課題です。適切な情報収集と住民の積極的な参画、そして専門家のサポートを得ながら、持続可能な管理体制を構築していくことが重要です。皆さまのスムーズな住まい取得のために、少しでもお役に立てれば幸いです。お気軽にお知らせください。
株式会社オオサワ創研
広島県呉市広文化町6-3
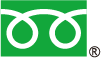
不動産事業部 松島 豊